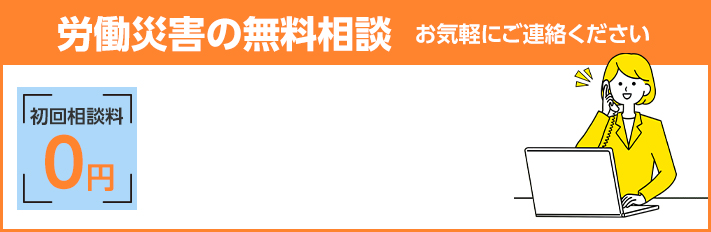労災認定とは、労働基準監督署が、労働者の仕事中や通勤中に生じたケガや病気等を労働災害(労災)として労災保険の給付対象になるかどうかを判断・認定することをいいます。
労災として認定されると、被災労働者が労災保険から療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの各種給付等を受けることができるようになります。
労働者本人や遺族等による労災保険の請求(労働者災害補償保険法12条の8第2項)がきっかけとなって労災認定がなされますが、請求にあたっては、各種給付ごとに必要な書類を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。
本来は労働者本人や遺族等によって申請手続がされることになっていますが、一般的には、会社の総務部が手続をして労働基準監督署に書類を提出しています。
各種給付ごとの必要書類(具体的な給付の内容については「労災保険とは」の項で説明いたします。)
1.治療費の補償給付
被災労働者自らが治療費を負担せずに、労災保険から病院に治療費を支払ってもらうために「療養給付請求書」が必要になります。被災労働者が療養を受けている医療機関を通じて、所轄の労働基準監督署に提出します。この際、医療機関が作成した診療報酬明細書(レセプトと呼ばれています)も併せて提出されます。レセプトは医療機関が提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません
2.休業中の補償給付
労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、「休業補償給付支給請求書」を用意する必要があります。この請求書に、事業主および医師の証明等を受けたうえで、原則として被災労働者自身が労働基準監督署に提出をします。この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。
3.後遺障害の補償給付
治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、被災労働者が「障害補償給付支給請求書」を作成し、医師の診断書等と併せて労働基準監督署に提出します。いわゆる後遺障害の認定申請です。この資料を基に、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級が確定することになります。
4.その他(被災労働者が死亡した場合の給付)
被災労働者本人死亡時の補償給付及び葬祭料は、それぞれ「遺族補償給付請求書」と「葬祭料請求書」を遺族が作成し、その他必要書類とともに労働基準監督署に提出します。